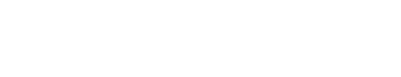城ノ山古墳の副葬品と埴輪
城ノ山古墳は、兵庫県朝来市和田山町東谷にある、山の尾根の先端に築かれた古墳です。直径36m、高さ5mの円墳で、4世紀後半につくられました。埋葬施設から青銅鏡をはじめとして石製の腕飾りや容器、首飾りなどが見つかっています。1971年の国道9号を新たにつくるさいに発見されました。
城ノ山古墳の副葬品は一括して国の重要文化財に指定されています。銅鏡6点、剣などの金属器具13点、勾玉など80点以上が含まれています。これらは、古墳時代前期の副葬品の特徴を強く示すものです。
青銅鏡
-Bronze Mirrors-

城ノ山古墳の6枚の銅鏡は、3枚ずつ2組に分けて、古墳の頭部と足元に配置されていました。珍しい琥珀やガラスの勾玉など、さまざまなビーズが添えられていました。考古学者は、この配置が悪霊を追い払うことを目的としたものだったのではないかと考えています。
そのうち 3 枚の鏡は、縁の三角形の断面と、3 人の神と 3 匹の動物が交互に描かれた同様のデザインで注目に値します。これらのデザインは、現在の奈良県にあり後に日本初の統一国家となる大和王権の中枢域では一般的であり、大和王権と但馬の間に確立されていたつながりをさらに強調しています。他の 3 つの鏡には、神話上の獣、絡み合う唐草模様、正方形の幾何学模様に配置された 8 羽の鳥など、さまざまなデザインが施されています。
玉杖・合子・石釧
-Royal Cane,Vessels,Bracelets-

刀剣
-Swords-

城ノ山古墳では、王権の他の象徴である儀式用の杖に取り付けるY字型の先端や、蓋のない脚付きの壺などの石の製品も見つかりました。これらの副葬品の正確な儀式的機能は不明です。
金属製の武器や道具も埋葬者の足元に積み上げられていました。武器は長剣2本と短剣1本で、道具には斧、槍がんなと呼ばれる柄の長い手斧、小さな刃物が含まれていました。この遺物は、茶すり山古墳に埋葬されている武勇に優れた王よりも小規模な統治者を示唆しており、まだ大和王権の全面的な軍事的支援を獲得していない地域の人物であることを示しています。
城ノ山古墳の建設は他の側面でもこの解釈を裏付けています。そのデザインは非常に簡素で、葺石や屋根石で覆われておらず、他の古墳に見られるような埴輪もありません。これは、大和王権がその周辺を統治する王たちに対して初めてその権限を拡大し始め、武器や専門知識とともに古墳建設などの技術を供給し始めた歴史的瞬間を示唆しています。
城ノ山古墳は、現在の豊岡市の北にある小見塚古墳とほぼ同時期に築造されたため、考古学者らはこの古墳の2人の埋葬者が南北に別々の王国を持っていたと考えています。1世代か2世代以内に、おそらく大和王権の支援を受けて、1人の武勇に優れた王が但馬全土を統一することになったのでしょう。池田古墳と茶すり山古墳は、数キロ離れた現在の朝来市に相当する地域に位置しており、最初の2人の王が埋葬されていると考えられています。両者が統治の拠点として、古くから貿易と交通の要衝である朝来を選んだことは重要な意味をもっています。