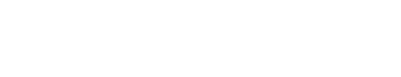但馬王の秘宝:茶すり山古墳の副葬品と埴輪
茶すり山古墳の2つの埋葬施設には副葬品が納められており、これらは合わせて国の重要文化財に指定されています。発掘調査では、武器や甲、道具や農具、青銅鏡、勾玉やその他の玉、さらには装飾用の髪櫛など、合計600点の個別の品物が見つかりました。また、古墳には多くの埴輪が見つかっています。これらの品物の詳細は、この墓の主要な埋葬者が大和王権と強いつながりを持っていたことを示唆しています。
襟付短甲
-Body Armor-
(復元品)





蛇行剣
-Serpentine Sword-
(復元品)

2 つの埋葬施設のうち、最初の埋葬施設はより大きく、明らかに武勇に優れた性格を持つ尋常ではない数の副葬品が納められていました。考古学的に最も重要な発見は、2 領の甲冑でした。 ひとつ目は、多数の薄い三角形と長方形の鋼板から作られ、革紐で綴じあわされて、襟付きの胴鎧を形成しました。同じ構造の一致する兜も見つかりました。これは大和王権の中枢域である近畿の外で発見された、この種の最初の甲冑でした。朝来市埋蔵文化財センターには複製品が展示されています。革紐の代わりに白い紐が使われており、綴じ目がより鮮明に見えるようになっています。
2 番目の甲冑は長方形の鋼板で構成されており、これも革紐で組み合わされていました。襟はなく、革紐ではなくリベットで留められた鋼板製の似合わない兜と組み合わせられていました。この不一致は、この鎧が実際に使用されたことを示唆しています。
最初の埋葬施設には、30 本の剣、数十本の槍や鉾、約 400 本の矢も埋葬されていました。甲冑と同様に、これらの武器は明らかに大和王権によって供給されたものであり、埋葬者がより強力な大和王権に支援された地域の戦士の王であったことのさらなる証拠と考えられています。
埋葬された武器のすべてが戦争を目的としたものではありませんでした。例えば、茶すり山古墳から出土した「蛇行剣」は、波打つ刃が戦闘では実用的ではなかったため、儀式の機能を持っていた可能性が高いとされています。
首飾り
-Necklace-

第 2 の埋葬施設には、はるかに少ない副葬品が納められていました。金属工芸品の大部分は農業、工芸、建設用の道具でしたが、2本の剣を含む少数の武器が体の両側に平行に置かれていました。 2つの装飾用櫛の金具も見つかりました。これらすべては、最初の埋葬者とは明らかに異なる人生の役割を示唆していますが、考古学者はその役割の正確な性質が何であったかについては不明としています。
青銅鏡
-Bronze Mirrors-

古代東アジアでは、青銅鏡は権威の象徴であり、儀式の目的でよく使用されました。それぞれの鏡は鋳造された青銅の円盤で、片面は華麗な装飾が施され、もう片面は滑らかに磨かれていました。保管安置されていないときは、首に掛けられており、これを持っている人はまばゆい太陽光を捉えて、光の方向を変えることができました。茶すり山古墳からは第1埋葬施設から3枚、第二埋葬施設から1枚の計4枚の鏡が出土。全てが実際の埋葬者と同じ木造埋葬施設の区画に埋葬されていました。
茶すり山古墳に埋葬されている鏡のうち1枚は中国製で、残りは中国製をモデルに日本で鋳造されたものです。その装飾デザインは、龍からシンプルな幾何学模様まで多岐にわたります。
家型埴輪
-Buildig-Shaped Haniwa-

埴輪は、日本の古墳やその周囲で見つかった土製の品の総称です。茶すり山古墳から出土した埴輪には、円筒埴輪、朝顔形埴輪、家形埴輪、衝立形埴輪などがあります。他の種類も存在していたようですが、現在は破片しか残っておらず特定できません。
円筒埴輪は、中空で土管状の土製の円筒です。朝顔埴輪も似ていますが、朝顔の花に似た縁が広がっています。どちらのタイプも側面に穴があり、茶すり山古墳ではこの穴に他では見られない左回りの渦巻き模様が施されています。これらの埴輪は古墳の周囲を示すために使用されていたため、考古学者らは、渦のような模様が侵入者を遠ざけるべきだという警告だったのではないかと考えています。
茶すり山古墳で見つかった3基の家形埴輪は、当初は古墳頂上の第1埋葬施設の上に置かれていましたが、その下にあった木製の棺が倒壊した際に墓内に落下しました。家形埴輪のうち ひとつは入母屋造りの特徴的な屋根を持ち、他の 2 つはより単純な構造です。それらはおそらく埋葬者の住居や倉庫を表していると考えられます。近くの柿壺遺跡の発掘に基づいて、考古学者は住居が四方に10メートル以上あった可能性があると考えています。
衝立形埴輪は、古代日本の宮殿や神社で使用された装飾品のモデルでした。茶すり山古墳におけるその存在は、日本の葬送儀式の歴史と、大和王権と周囲の小規模な政治の地方王との関係に貴重な光を当てています。